社会的インパクト評価と進捗報告
北海道における民間ロケット打上げ実験射場整備案件
2025年10月15日 現在
| 助成金額 |
100,000,000円 |
|---|---|
| 助成先 |
SPACE COTAN株式会社(スペースコタン、北海道大樹町、以下「SC」) |
| イシューファインダー |
小田切 義憲 SC代表取締役社長兼CEO |
| 解決を目指す社会課題 |
サブオービタルロケット実験射場不足に伴う、宇宙産業の初期フェーズ発展遅延 |
| トピックスリリース |
社会課題「サブオービタルロケットの実験射場が不足している!!」
多くの民間ロケット事業者や大学は、将来的な人工衛星打上げロケット(オービタルロケット)を見据えた初期のロケット開発として、高度100kmの宇宙空間に到達する弾道飛行を行うサブオービタルロケットの実験射場を求めています。しかしながら、国内では民間や大学などがサブオービタルロケットを打上げることができる実験射場が不足しています。北海道大樹町がSCと共に取り組む北海道スペースポート(以下「HOSPO」)の活動では、民間にひらかれた商業宇宙港で、SCはHOSPOを管理・運営しています。将来的には、オービタルロケット打上げと人工衛星データ収集利活用を通じた様々な社会課題解決(温室効果ガス測定・災害対応・通信格差是正など)やアジア地域での民間宇宙産業の振興を実現することで、社会の持続的発展への寄与を目指しています。
三井物産は本基金を通じ、SCが進めるサブオービタルロケット実験射場整備を支援し、業界知見を活かしながら地元企業や自治体ほかステークホルダーへの働きかけや、国内外の民間ロケット事業者へのマーケティング活動、大学などのサブオービタルロケット打上げを支援し、日本国内の宇宙産業の成長やSCが目指す社会課題解決の実現に貢献します。
HOSPOロケット打上げ映像
社会的インパクト評価(ロジックモデルとKPI)
イシューファインダー&共創者対談
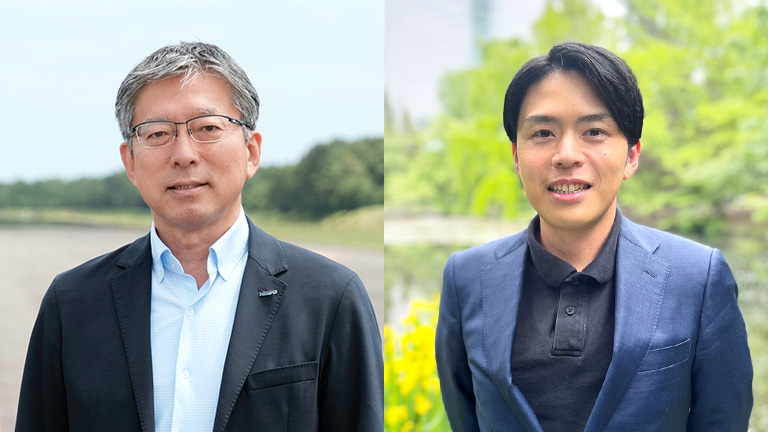
聞き手: 木村(三井物産、右) 答え手: 小田切(SPACE COTAN、左)
木村: はじめに、SPACE COTAN創業のきっかけを教えていただけますか?
小田切: もともと大樹町で宇宙の取り組みが始まったのは1985年頃のことです。21世紀を控え「次に何をするべきか」が全国的に議論されていた時期で、北海道東北開発公庫(現:日本政策投資銀行)や北海道庁が中心となって、いろいろな産業の掘り起こしを行っていたんです。北海道で15ほどの構想が立ち上がって、その中のひとつが「大樹町への宇宙産業基地誘致に取り組む」というものでした。その流れの中で「HOPE」という、日本版スペースシャトルを開発しようというNAL(航空技術研究所)・NASDA(宇宙開発事業団。NALともども現在のJAXAに統合)のプロジェクトが立ち上がりまして、その実験候補地として大樹町が浮上しました。これをきっかけに、大樹町も本格的に中央省庁に掛け合って滑走路の整備を進めたり、宇宙港の構想を具体化させていきました。このプロジェクトはサブスケール実験までで終了してしまいましたが、この動きが現在の北海道スペースポート(HOSPO)に繋がることになりました。

その後、歴代町長を始めとする大樹町の皆様の強い思いで受け継がれてきた宇宙の取り組みが、再び大きく盛り上がったのが2010年代の後半のことです。民間の宇宙産業が進展してきた流れを受け「これは改めて本格的にやっていくべきだ」という機運が高まりました。それまで進めてきた「町の事業」から更にステップアップし、しっかりとした会社組織を作って取り組もうということで、2019〜2020年頃に構想が固まり、2021年にSPACE COTANを設立しました。現在5年目になりますが、大樹町と二人三脚で歩みを進めている会社です。
スタートのタイミングがちょうどコロナ禍と重なっていたため、具体的な事業をすぐに始めることは難しい状況で、当初は調査・研究や計画立案を先行させました。2022~2023年頃には事業計画や将来構想が少しずつ具体化し、並行してちょうど国の宇宙基本計画の改定や宇宙技術戦略の策定も進み、その具体的施策として宇宙戦略基金が創設され、2024年から一気に事業が加速したというのが現在までの流れです。
木村: こうして構想が実現に向かって動く背景には、関係者の熱い思いがあったからこそで、やはり人の熱意が欠かせないのだと実感します。
小田切: そうですね。勿論いくつかの偶然も重なったとは思いますが、やはり最終的には「人の思い」が全てだと思います。やると決めた人たちの熱意がなければ物事は動かないですし、「人口も減っているし、もうこのへんで…」と諦めてしまえば、そのまま終わっていたかもしれません。本当に、皆さんの頑張りがあってこそ、ここまで来られたのだと思います。
木村: 三井物産共創基金のことは、どのようにして知ったのでしょうか?

小田切: もともとは、北海道経済連合会が進めていた「2030年時点の『宇宙版シリコンバレー』 実現に向けたアクションプラン」のプログラムがきっかけでした。この中で、木村さんを含む三井物産北海道支社の皆様に大樹町にお越しいただき、我々が目指していた「HOSPOを核とした宇宙版シリコンバレー構想」をご紹介できたことが、大きな転機になったと思っています。このご訪問がちょうど三井物産共創基金が始まるというタイミングと重なり、本基金に関する具体的なお話をいただきました。
我々は第1号案件だったこともあり、試行錯誤を重ねましたが、その中で「こういう形にしていくのが良いのではないか」と共創者の皆様にうまく導いていただきました。そのおかげで、方向性を見い出すことができ、本当にありがたかったと思っています。
木村: むしろ、こちらが小田切さんに導いていただいたと感じています。私たち北海道支社としても宇宙事業、特に射場事業にどう関わるべきか悩んでいた時期でした。そこに三井物産共創基金が立ち上がり、民間ロケット向け射場不足という課題に一緒に取り組み、米国のような民間宇宙産業を作り上げるという方向性であれば、我々としても長期的視点で関与できるのではと考えました。制度立ち上げの時期で混乱もありましたが、むしろその過程を通じ、将来的にはオービタルロケット打上げと人工衛星データ収集利活用を通じた様々な社会課題解決(温室効果ガス測定・災害対応・通信格差是正など)に向け「一緒に事業を作っていく仲間」という関係を築けたことは結果的に非常に良いプロセスだったと感じています。
小田切: 「一緒に苦労し、汗をかく」というのは、仕事を進めていく中でとても大切な要素だと思います。そういう意味でも、この期間は「意識醸成の場」として大変貴重だったと感じています。
木村: 実際に三井物産共創基金を活用してみて、どんな印象を持たれましたか?
小田切: 現在の我々の立場としては、大樹町が射場を整備し、それを我々がサービスプロバイダーとして運営・管理するというのが基本スタンスです。自社で多くの資産を保有する前提ではないため、何か具体的に設備を整えるとなると、資金調達に苦労することも多く、今回、三井物産共創基金から助成をいただけたのは非常にありがたいことでした。特にサブオービタルロケット打上げのための射点(LP12/Launch Pad)を整備できたことは大きかったです。この整備資金を確保するには融資を受けることを当初考えておりましたが、本基金を活用させていただくことができました。そのおかげで台湾資本のロケットの打上げが実現でき、本当にうれしく思っています。
木村: そうですね、今回、三井物産共創基金で整備された射点が、日本で初めての海外資本ロケットの打上げの舞台となりました。私も打上げに立ち会わせて頂き、必ずしも全てが予定通りではありませんでしたが、本基金申請にも謳った「アジアでの民間宇宙産業の振興」のキックオフとなれたことは本当に感慨深いものがありました。
小田切: 打上げが終わった段階で、台湾企業の社長も「次回もここから打上げたい」と明言してくれました。次回はぜひミッションを達成できるよう、引き続き様々な支援していきたいと考えています。
木村: 共創者に期待することや、連携で生み出されている価値について教えていただけますか?
小田切: 私たちは「北海道に宇宙版シリコンバレーを作る」と謳っており、今後は北海道内の企業と、より実質的なビジネス連携が必要になってくると考えています。たとえば、三井物産共創基金で取り組む予定の施設整備も、地元企業との連携で進めています。宇宙戦略基金の案件でも、地元の電気工事会社や建設会社に発注が生まれていますし、その他にも道内企業にお仕事を依頼し始めています。こうした経済的な波及効果は、地域にとって大きな意義があると感じています。三井物産共創基金を通じてこのような動きが生まれていること自体が、価値あることだと捉えていますし、同時にそれをきちんと外部にも発信することも重要と考えています。
木村: 宇宙戦略基金の話もありましたが、SPACE COTANが社会課題の解決を目指す上で、三井物産共創基金以上に必要なものは何だと思われますか?
小田切: まだまだ乗り越えるべき課題は多くあります。目の前のものとしては、国が目標に掲げる高頻度打上げの実現を目指す射場「Launch Complex 2(LC2)」の整備資金確保が喫緊の課題です。宇宙戦略基金は文部科学省の調査研究費であり、いわゆる「射場等の整備費」には充当できません。LC2の整備にはコアとなる施設だけでも数百億円単位の資金が必要になると見込まれており、その財源をどのように確保するかが論点となります。社会的インフラ施設とも言えるロケット打上げ射場を民間資金のみで整備することは現実的ではありません。公共インフラと位置付けられることから、国、自治体等公的機関による支援が前提になると考えています。我々もスキーム案構築に参画し、政府に要望できる状態を準備する必要があると考えています。こうした要望に当たっては、三井物産の皆様のアドバイスや働きかけは重要ですし、企業ならびに経済団体の後押しも大きな意味を持つと思っています。
木村: 宇宙港は宇宙産業の基盤という役割期待もあり、運営に際しては公的支援が前提となっているのが世界的な潮流です。その意味で国・自治体や各団体との連携は不可欠だと実感しており、ぜひ協力させていただきたいと思っています。
木村: 今後、三井物産共創基金やそのエコシステムにどのようなことを期待されていますでしょうか?
小田切: 三井物産共創基金の制度は今後も続いていくものと理解しています。そういった意味で、我々の取組みが「ベストプラクティス」として少なからず次の方々に共有できるのであれば、それは意義があることだと思っています。また、「三井物産共創基金のOB/OG会=アルムナイ」のようなネットワークができて、定期的に集まり「その後どうですか?」みたいな話ができる場ができるといいなと思います。業種・業界が全く異なる人たち同士のつながりから、新しい発想や事業のヒントが得られるのは価値があると思っています。やはり、同じ業界内だと、どうしても知っている話しか出てこないんです。でも、まったく異なる領域の話を聞いて「それってうちにも応用できるんじゃないか」と気づくことがある。そういう意味で、業種を超えた横のつながりが自然にできる仕組みがあると嬉しいですね。
木村: 素晴らしいご提案をありがとうございます。当社には様々な事業領域があり、分野横断的な掛け算としての業際の力を重視しています。三井物産共創基金のネットワークを通じこの業際的なアイデアが実現できればと思います。
木村: 戦前の旧三井財閥の歴史を紐解いてみると、かつての北海道開拓に深く寄り添ってきたことがわかります。当時、炭鉱・木材・金融などの各分野で「新しい産業をつくる」という開拓者精神で取り組んでいたのと同様、今の時代において「宇宙」という新産業を北海道で育てていくプロセスに関われることを、とても光栄に思っています。
小田切: ありがとうございます。私もこの地の歴史を勉強する中で面白いことを知りました。一時期、北海道が日本の産業のエンジンだった時期がありました。北海道が日本で人口が一番多かった時期もあるんです。これは、誰かが「ここに資源がある」「ここでやろう」と旗を立てたから実現したことで、誰かの意思が地域を動かしたわけです。宇宙産業もそれに近いビジネスモデルだと思っています。
木村: まさに「北海道が再び日本のエンジンになる」時代が来たのかなと実感します。小田切さん、本日はありがとうございました。SPACE COTANの今後の発展と日本の宇宙産業の未来に期待しています。
活動のハイライト
1.サブオービタルロケット実験射点「LP12」が完成
弾道飛行を行うロケット(サブオービタルロケット)の射点「Launch Complex 1 - Launch Pad12(LC1 - LP12)」が完成(2024年7月)。
2.国内初となる海外資本のロケット会社の打上げ実験を実施
台湾TiSPACE社の日本法人「jtSPACE株式会社」のサブオービタルロケット「VP01」の打上げを2025年7月12日に実施。国内で海外資本のロケットが打上げられた初の事例となった。
3.海外のロケット事業者とのMOU:2件の目標に対し3件の締結
台湾TiSPACE社はじめとして、三井物産出資先の米Firefly Aerospace社を含む3社とのMOUを締結。目標値の2件を上回る3件を達成(2025年8月時点)。
4. 「HOSPO SUPPORTERS」登録企業:220社(含団体)の目標に対し185社
大樹町への企業版ふるさと納税を通じて、軌道投入用ロケット射場「Launch Complex 1(LC1)」の整備や宇宙関連ビジネス推進の支援を行った企業を登録する「HOSPO SUPPORTERS」の登録企業が185社となる(2025年6月時点)。 引き続き、2026年3月末までに220社の登録を目指す。
三井物産のマテリアリティ(重要課題)
三井物産は、「世界中の未来をつくる」を企業使命に、さまざまなステークホルダーの期待と信頼に応え、大切な地球と人びとの豊かで夢あふれる明日を実現すべく、サステナビリティ経営の重要課題としてマテリアリティを特定しています。本件は、6つのマテリアリティの中でも、特に「持続可能な安定供給の基盤をつくる」、「健康で豊かな暮らしをつくる」の実現に資する取り組みです。
-
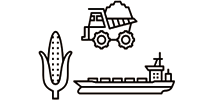
持続可能な安定供給の基盤をつくる
-

環境と共生する世界をつくる
-

健康で豊かな暮らしをつくる
-

人権を尊重する社会をつくる
-

「未来をつくる」人をつくる
-

インテグリティのある組織をつくる