社会的インパクト評価と進捗報告
アフリカにおけるヘルスケアイノベーションハブ構築案件
2025年7月16日 現在
| 助成金額 |
66,995,000円 |
|---|---|
| 助成先 |
CA Medlynks Kenya Limited(CAメドリンクスケニアリミテッド、ケニア共和国・ナイロビ、以下 「CA MEDLYNKS」) |
| イシューファインダー |
嶋田 庸一 CA MEDLYNKS CEO |
| 解決を目指す社会課題 |
アフリカにおいて蔓延する感染症、疾患の研究・診断インフラ不足 |
| トピックスリリース |
社会課題「アフリカにおける疾患診断のインフラがない!」
アフリカではHIV/AIDS・結核・マラリアなどの三大感染症、顧みられない様々な感染症がいまだに根強く残るほか、がんや生活習慣病などの非感染症の脅威も急増しています。こうした疾患の研究・診断には本来公的機関のみならず、民間の研究者・研究機関・企業の果たす役割が大きいものの、研究・診断を行うための施設・機器不足、また活動を推進するための支援が求められています。
CA MEDLYNKSは、ヘルスケアスタートアップ企業である株式会社Connect Afya(コネクトアフィア、兵庫県たつの市、代表取締役社長:嶋田 庸一)の子会社で、アフリカで検査インフラや診断サービスを提供しています。さらに現地の医療機関・研究者・研究機関と協働して上記課題を解決するエコシステムを構築し、アフリカにおける疾患研究・診断サービスの進展を進めています。三井物産は本基金を通じ、アフリカでの事業経験やネットワークを活用し、研究者との連携を推進し、現地の関係者が最新研究・診断機器にアクセスできるイノベーションハブの構築を支援します。
社会的インパクト評価(ロジックモデルとKPI)
イシューファインダー&共創者対談

聞き手: 宮本(三井物産) 答え手: 嶋田(Connect Afya)
宮本: 嶋田さん、まずはConnect Afyaを立ち上げたきっかけを教えていただけますか?
嶋田: 新卒で製薬企業や医療機器メーカーの営業戦略を支援するコンサルティング会社に勤めていましたが、その傍らで知人のウガンダやケニアといったアフリカでのスタートアップ立上げを手伝っていました。その活動を通じて、アフリカで見る現場の課題を直接解決したいと思うようになりました。
その後、フランスに留学中したのですが、その時にケニアに自分でリサーチに行った際、現地の医療があまりに自分が日本などで見てきたものとかけ離れているのを目の当たりにして、医療インフラの改善に取り組みたいと強く感じました。
特に、適切な診断が受けられないことで病気が見過ごされてしまう現実に衝撃を受け、検査の普及を通じて医療全体の流れを作り出したいと考え、Connect Afyaを立ち上げました。
宮本: ケニアでの経験が原点なのですね。適切な診断が受けられない現実というのは、私たち日本ではなかなか想像がつきにくいですが、そこで起業という決断をされたのがすごいですね。

宮本: 三井物産共創基金のことは、どのようにして知ったのでしょうか?
嶋田: 接点のあった中東三井物産の方とお話させていただいた際に「三井物産共創基金って知ってますか?」と教えていただいたのがきっかけです。資金提供だけでなく、事業を加速させるためのアドバイスやネットワークの支援が受けられると聞いて、「これは挑戦しないと」と思いました。また、三井物産さんのアフリカでの豊富なプロジェクト経験と信頼性も大きな魅力でした。
宮本: 資金提供だけでなくアドバイスやネットワークの支援も受けられるのは、起業家にとって非常に心強いですよね。
宮本: 実際に三井物産共創基金を活用してみて、どんな印象を持たれましたか?
嶋田: ちょうど資金調達を行っていたこともあり、正直、最初は「資金が得られればいい」くらいに思っていた面もあったのですが、それ以上の価値があるとすぐに気付きました。資金提供だけでなく、現地での事業展開のための具体的なアドバイスや、重要なネットワークの構築をサポートしてもらっています。
特に、現地パートナーと連携する際、三井物産さんがその橋渡し役になってくださるのは大きな助けです。本基金が三井物産さん役職員の共創者との「共創」を掲げているのは本当にその通りで、単なるお金のやり取りだけではなく、一緒に価値を作り出していくという姿勢を強く感じています。
宮本: 「共創」という言葉が、ただのスローガンじゃなくて、実際の支援に落とし込まれているというのは嬉しいですね。現地での連携に三井物産がどのように関わっているのか、もっと詳しく聞きたくなります。

宮本: 共創者に期待することや、連携で生み出されている価値について教えていただけますか?
嶋田: 共創者には、現地の実情に詳しく、課題解決に情熱を持っていることを期待しています。特に、テクノロジーや物流の専門知識を持つパートナーと組むことで、今までできなかったことができるようになっています。
例えば、物流の効率化や感染症対策のためのデータ分析技術の導入など、具体的な成果が生まれています。こうした連携がなければ、私たちだけでは成し遂げられなかったことばかりです。これからもお互いの強みを活かして、より多くの価値を生み出していきたいですね。
宮本: お互いの強みを活かして新しい価値を生み出しているのがよく伝わってきます。物流の効率化やデータ分析技術の導入というのも、現地でのインパクトが大きそうです。
宮本: この社会課題を解決するために、三井物産共創基金以上に必要なものは何だと思われますか?
嶋田: やはり現地の人たちとの信頼関係が一番大事だと思います。それがなければ、どんなに素晴らしい仕組みを持ち込んでも定着しません。信頼の礎は、地道にやっている姿を見せることだと思うので、その点はいつも意識しています。
それと、政策的な後押しも必要です。例えば、政府や国際機関との連携を深めることで、より広範囲に影響を与えることができます。こうした取り組みが、社会課題の解決には欠かせないと思います。
宮本: 信頼関係や人材育成というのは、本当に重要ですよね。それがあってこそ、現地の課題に根付いた解決策が実現できるのだと思います。政策的な後押しについても、やはり現地の政府や国際機関との関係構築が鍵を握りそうですね。
宮本: 今後、三井物産共創基金やそのエコシステムにどのようなことを期待されていますでしょうか?
嶋田: もっと多くのプレイヤーがこのエコシステムに参加してくれると嬉しいです。特に、私たちが活動しているアフリカのような地域では、まだまだ解決すべき課題が山積みです。そういった課題に取り組む新しいプロジェクトがどんどん生まれることを期待しています。
それから、本基金を通じて成功した事例が次世代の企業や起業家にとってのロールモデルになっていくといいですよね。それがまた新しい挑戦を生み出し、さらに大きな価値を生み出す循環ができれば素晴らしいと思います。
宮本: 確かに、成功事例が次世代に引き継がれていくエコシステムができれば、基金の価値もさらに広がりますね。新しい挑戦が次々と生まれる場として、これからも進化していくことを期待しています。
宮本: 嶋田さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。
活動のハイライト
1.イノベーションハブがローンチ
最先端の遺伝子シークエンサーを含めた東アフリカ最大規模の研究拠点が無事に稼働開始(2024年7月~)し、設備を利用した初の研究案件が実施され、イノベーションハブのインフラを用いた初の研究が実施される(2024年12月)。
2.研究機関・アカデミアとの間の研究者がパートナーシップが進む
ケニア国内の10を超える研究機関・アカデミアの研究者がパートナーとしてイノベーションハブ内で行われるトレーニングや研究相談会に参加し、施設の設備を使った今後の具体的な研究を相談するように(2024年12月時点)。
3.研究実施:実施研究・論文発表数は2026年までに10の目標に対し実施済1件。2025年中に実施を控えた研究数は7件。
加えて、ケニア国内の研究者からの研究実施のみならず、日本の大学2校と研究サポートへ向けた提携協議中。
4.対外発信: 4件の目標に対し、2件の対外発信
2026年までの当初目標の4件の対外発信の実施に対し、日系・FT日経感染症会議、アフリカインベストフォーラムで本件取り組みを発信し、国内外の関心を持つプレーヤーを巻き込める体制を構築している。
三井物産のマテリアリティ(重要課題)
三井物産は、「世界中の未来をつくる」を企業使命に、さまざまなステークホルダーの期待と信頼に応え、大切な地球と人びとの豊かで夢あふれる明日を実現すべく、サステナビリティ経営の重要課題としてマテリアリティを特定しています。本件は、6つのマテリアリティの中でも、特に「持続可能な安定供給の基盤をつくる」、「健康で豊かな暮らしをつくる」の実現に資する取り組みです。
-
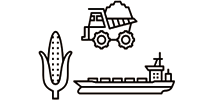
持続可能な安定供給の基盤をつくる
-

環境と共生する世界をつくる
-

健康で豊かな暮らしをつくる
-

人権を尊重する社会をつくる
-

「未来をつくる」人をつくる
-

インテグリティのある組織をつくる