社会的インパクト評価と進捗報告
ごみの自然界流出問題解決案件
2025年10月15日 現在
| 助成金額 |
98,068,000円 |
|---|---|
| 助成先 |
株式会社ピリカ(東京都渋谷区、以下「ピリカ」) |
| イシューファインダー |
小嶌 不二夫 代表取締役社長 |
| 解決を目指す社会課題 |
国内外におけるごみの自然界への流出 |
| トピックスリリース |
社会課題「ごみの自然界への流出が無視できない規模に!!」
近年、ごみ(特にプラスチック)の自然界への流出が増加しています。ごみの流出による悪影響は、生態系・産業など広範囲にわたり、気候変動と同様に、あらゆる国家・企業が無視できない問題になろうとしています。しかしながら気候変動問題との大きな相違点として、ごみの自然界流出問題においては明確な計測手法が確立されていません。
ピリカは、ごみの回収・調査に関するさまざまなサービスを開発するスタートアップで、車両に搭載したスマートフォンのカメラで路上のごみ画像を撮影し、AIを活用してごみ分布(場所・種類など)を調査するサービス「タカノメ」により、国内外の路上ごみの定量把握を行います。また、世界最大級の参加者数を誇り、ごみ拾い活動の輪を広げるごみ拾いSNS「ピリカ」では、同SNSを通じて市民が自発的にごみ拾いをした活動の様子や成果を1つのWEBページに集約・発信できる仕組みになっており、ごみ拾いの実施状況を効率よく定量的に把握できます。これらのサービスを通じ、清掃団体やNPO、行政、自治体などへ路上ごみ調査結果の報告や削減提言を行い、データを活用した清掃活動等の対策を推進しています。
三井物産は本基金を通じ、国内外の路上配送流通事業で有するアセットやネットワークを活用し、ピリカによる国内や北米・欧州・東南アジアにおけるごみ調査・対策網構築を支援し、国内外におけるごみの自然界流出問題解決に向けたサイクルを地球規模で加速させることに貢献します。
社会的インパクト評価(ロジックモデルとKPI)
イシューファインダー&共創者対談
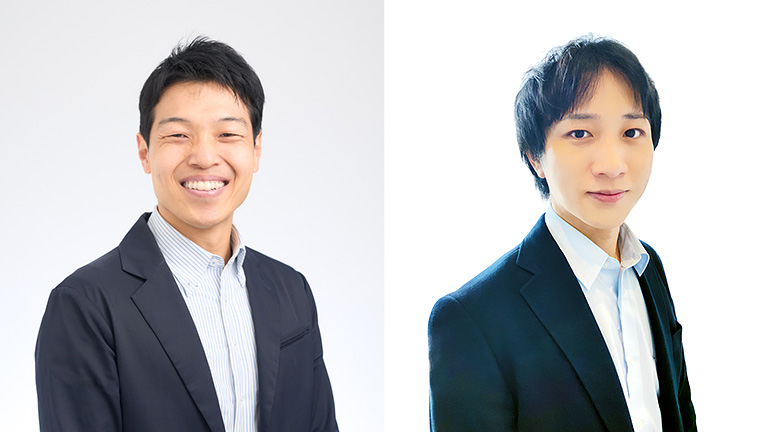
聞き手: 石田(三井物産、右) 答え手: 小嶌(ピリカ、左)
石田: 小嶌さん、まずはピリカを立ち上げたきっかけを教えていただけますか?

小嶌: 大学院を半年で休学して世界を旅していた際、訪れた全ての国で「ごみの自然界流出問題」が深刻な規模で広がっていることに衝撃を受けました。日本では見過ごされがちな課題でしたが、環境インフラが脆弱な地域では人々の生活にも直結する深刻な問題です。そうした背景から2011年にピリカを創業し、テクノロジーの力でごみ問題に取り組む道を選びました。
石田: 現場のリアリティから起業へとつながったのですね。その熱意が伝わってきます。
石田: 三井物産共創基金のことは、どのようにして知ったのでしょうか?
小嶌: 三井物産の方と以前から接点があり、三井物産共創基金について耳にしたことはありましたが、最初は「株式会社は対象外だろう」と思っていました。ですが、あるとき三井物産共創基金の担当の方から「ソーシャルスタートアップも対象ですよ」と教えていただき、これは挑戦すべきだと動き始めました。
石田: 実際に三井物産共創基金を活用してみて、どんな印象を持たれましたか?
小嶌: 最初は資金面での支援を得られるだけでありがたいという期待感でしたが、実際には事業の加速に直結する多くのサポートもいただき、大変心強いです。特に、共創者である石田さんをはじめとする三井物産の皆さんの現場目線でのアドバイスや、グローバルなネットワークの提供など、資金以上の価値を強く感じています。
石田: 国内外の流通に関するアセットやネットワークを有する当社と共創することによって、今までとは違う支援を受けられるのは大変心強いですね。

石田: 共創者に期待することや、連携で生み出されている価値について教えていただけますか?
小嶌: テクノロジーや流通インフラの知見を持つ方々と連携することで、私たち単体では難しかった課題解決が可能になっています。たとえば、AI搭載のアプリ「タカノメ」を使ったごみの可視化を小売業や飲食業の配送車両に実装できたのは、まさに三井物産のネットワークと知見のおかげです。
石田: 三井物産グループの車両で調査を開始したことにより、調査エリアの範囲を拡大できたことは大きな成果になったのではないかと思います。
石田: この社会課題を解決するために、三井物産共創基金以上に必要なものは何だと思われますか?
小嶌: この問題について、より多くの方に興味関心を持っていただき、それぞれの立場から課題解決に向けた取り組みに参画いただくことが不可欠だと考えています。特定の業種や組織だけで完結できる問題ではないからこそ、セクター横断的な協働を加速させていきたいです。
石田: ごみ問題解決に向けた土壌づくりをすることが重要であり、関係者を増やしていきながら、それぞれの立場で課題解決することが大切であると共感します。
石田: 今後、三井物産共創基金やそのエコシステムにどのようなことを期待されていますか
小嶌: 共創による協業や学びが連鎖的に生まれることで、社会課題に取り組む動きが加速していくことを願っています。今回、私たちが進めているごみ可視化の事業も、一つの成功事例として他の挑戦を後押しする存在になれれば嬉しいです。
石田: おっしゃる通りですね。私自身も小嶌様と共創することにより沢山の学びをさせていただいており、本基金を通じてイシューファインダーと共創者の挑戦の場となること、更には次世代への後押しとなれればと期待しています。
石田: 最後に、助成期間中及びその後も達成したい目標を教えていただけますか?
小嶌: 国内では小売業や飲食業との連携をさらに拡大し、効率的な調査体制を構築したいです。海外では、アメリカをはじめとする国々での事例を積み重ね、政府・NPOと連携して「ごみの可視化」が政策に取り入れられるような状況を目指しています。また、助成期間終了後も自立して事業を継続できるよう、ビジネスモデルの確立にも取り組んでいきます。
石田: 私たちもその実現に向けて、引き続き伴走させていただきます。本日はありがとうございました。
活動のハイライト
1.三井物産グループの車両を活用した調査を開始
三井物産グループの車両で調査を開始したことにより、関東エリア、関西エリア、九州エリアでの調査範囲が拡大。タカノメのサービス導入実績の中で、最大規模の調査体制を構築(中)。
2.国内の行政・自治体との連携:10件の目標に対し4件実施
三重県、滋賀県、網走市等との連携や、東京都の社会実装プログラム採択により調査網を拡充(2025年7月時点)。現在、導入検討中の自治体もあり。
3.海外調査国数:5カ国の目標に対し7カ国で実施
海外7カ国13都市における調査の累計走行距離は約3,000km(2025年7月時点)。米ハワイ州のNPOと連携しNPO・行政市場の開拓を開始、北米本土での行政との実績作りを進行中。
4.リリース発信:6件の目標に対し3件の発信
2026年3月までの当初目標に対し、支援事業採択のリリース1件、国内外での調査の広がりを2件発信(2025年8月時点)。今後は連携先を絡めた発信を模索中。
5.国際機関との連携:2件の目標に対し1件実施
JICAとの連携でペルーの自治区にタカノメ導入を実現、近隣区域の自治区での導入検討も進行中。
三井物産のマテリアリティ(重要課題)
三井物産は、「世界中の未来をつくる」を企業使命に、さまざまなステークホルダーの期待と信頼に応え、大切な地球と人びとの豊かで夢あふれる明日を実現すべく、サステナビリティ経営の重要課題としてマテリアリティを特定しています。本件は、6つのマテリアリティの中でも、特に「持続可能な安定供給の基盤をつくる」、「健康で豊かな暮らしをつくる」の実現に資する取り組みです。
-
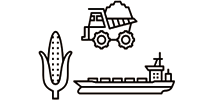
持続可能な安定供給の基盤をつくる
-

環境と共生する世界をつくる
-

健康で豊かな暮らしをつくる
-

人権を尊重する社会をつくる
-

「未来をつくる」人をつくる
-

インテグリティのある組織をつくる