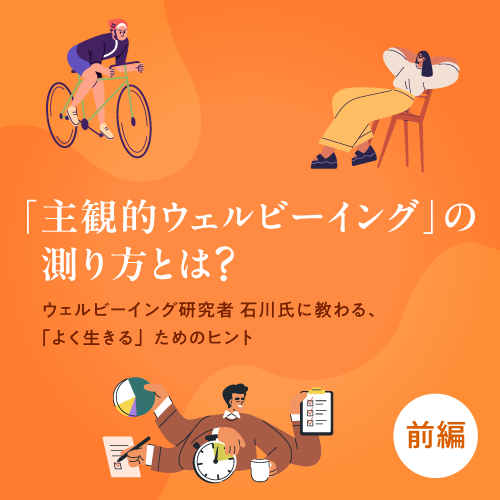女性をめぐる健康課題から考える 現代のウェルビーイングとは?[後編]
2024.12.25
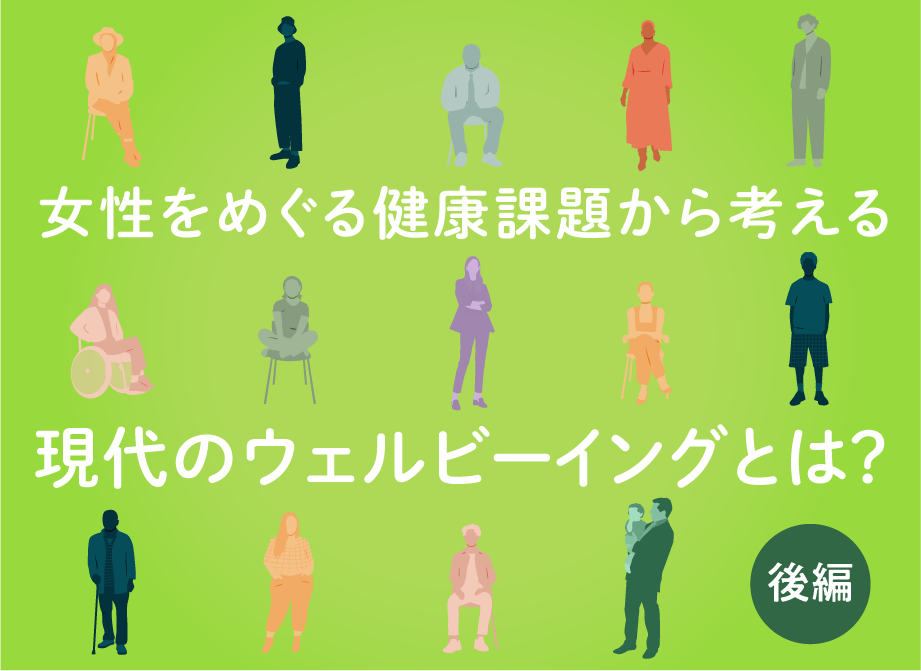
現代の女性の選択肢は広がり、ライフスタイルが多様化しています。しかし、依然として仕事と育児や家事、介護などとの両立や健康課題、それらに対する周囲の理解不足といった課題は残されたままで、社会全体のさらなる意識改革が求められています。
今回は、女性特有の健康課題の取り組みを通じて公正な社会の在り方を問い続けている小林味愛氏に、心身やライフスタイルの見つめ直し方、多様性が尊重される組織づくり、そして、より公正な社会の実現に向けた想いについてお伺いしました。その後編をお届けします。
前編はこちら
健康課題に取り組んだ先に見える組織の姿

女性特有の健康課題は、「3つの要因」が重なると悪化するといわれています。1つ目の要因は、女性ホルモンの減少など「女性の体の仕組みに起因する要因」です。2つ目は、仕事やプライベートでのタスクやストレスの多さといった「環境的な要因」です。現代社会では、女性の役割を固定的に捉える傾向が少なからずあり、それが知らず知らずのうちに女性に負担をかけているケースがみられます。3つ目は、「個人特性における要因」です。これは、「全て自分でやらなければ」という性格から、自分を必要以上に追い詰めてしまうケースとなります。
現在、私たちは企業向けに睡眠計測やカウンセリングプログラムを提供していますが、仕事で重要なポジションを担いながら、育児や介護、家事などの全てを背負いこむ女性が少なくありません。日中は部下の教育で忙しく、自分の業務に着手できるのは24時以降というケースも珍しくないのが現状です。
このように女性に過度に負荷が生じる社会環境では健康を害してしまうのは当然ですが、健康管理は自己責任だと捉えられることが多いのが現状ではないかと思います。女性個人の意思や自己責任の問題として片付けるのではなく、社会全体で問い直す必要があると考えています。
近年は、女性の健康課題を理解し、公正な職場環境の実現を目指す研修を実施する企業や自治体も増えてきましたが、具体的な施策を策定し、意識改革を進めるのは難しいという声も耳にします。そこで、私たちは医師や大学教授と連携し、「組織内のアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)に気づき、それを改善する行動を起こす方法」をテーマに、アクティブラーニング型の研修を企業や自治体へ展開しています。
研修では、全ての受講者に課題を「自分ごと」として捉えてもらうために、どのような工夫をされていますか?
研修では、男女問わず社員全体が受講するケースから、受講者が経営層となるケースなどさまざまな形で実施しています。男性社員にとっては、女性の健康課題や女性活躍推進に対して受け身の姿勢になりがちであることも少なくありません。そのため、「受講者が興味を持てる文脈に落とし込む」ことが重要なポイントとなります。
例えば、経営層を対象とした研修では、経営戦略の一環として女性の健康課題を位置付け、提示することで関心を引き付けることができます。一方、人事部を対象とした研修では、社員が高いエンゲージメントを維持しながら働き続けるための組織的な重要性にフォーカスすることで、効果的にアプローチできます。このように、受講者の属性や、組織の課題を事前にヒアリングした上で、研修内容をアレンジしながら展開しています。
また、研修プラグラムの一環として、日本で初めて「生理を取り巻く課題」にフォーカスした映画を制作した監督にオリジナル研修映像を制作いただきました。この映像は、職場に潜むアンコンシャス・バイアスをテーマに、さまざまな健康課題をストーリーの中に盛り込んでいます。日常的によく見られる場面に隠れているアンコンシャス・バイアスについて話し合うことで、受講者が自然と気づきを得られる参加型の研修となっています。こうした工夫を通じて、受講者一人ひとりが研修のテーマを身近に感じ、課題を「自分ごと」として捉えられるようにしています。
心地よさを感じる感性に蓋をしないで

ご活動を通して、どのような社会を実現したいとお考えですか?
私たちは、地域やお客様、取引先、協業先など、関わる全ての人々の幸せが循環していく、温かみのある共同体をつくりたいという想いで事業に取り組んでいます。女性特有の健康課題に悩んでいる方々に製品やサービスを届けるだけでなく、それを支える社会のインフラそのものを整備していくことも重要だと考えています。私が立ち上げた小さな一企業だけでできることは限られています。そのため、私たちだけではなく、さまざまな企業や団体と連携しながら事業の取り組みを拡大させていきたいと考え、いくつかの協業事業を進めています。例えば、働く更年期世代の女性を対象とした睡眠改善をテーマに、パラマウントベッド社と共同研究を行っています。この研究から得られた知見をベースに、質の高いサービスを創出し、より多くの人々に貢献してきたいと考えています。
最後に、「女性のウェルビーイング」をどのようにお考えですか? 読者へのメッセージをお願いします。
ウェルビーイングという考え方に性差はなく、究極的には「自分の人生を自分で選び、主体的に歩んでいくこと」だと思っています。ただ、人生における選択は、住まいや家庭、職場環境など、複合的な環境要因に大きく左右されるものでもあります。
いわゆる「バリキャリ」だった20代の私は、一つの成功モデルのようなものに囚われて生きていました。今思えば、日々の中にある「違和感」を直視し、その存在を認めてしまったら、社会から振り落とされるのではないかという恐怖感から、自信の感覚や感性に蓋をして日々を過ごしていたように思います。そのことに気がつけたのは、自分の生活環境を大きく変えた時でした。福島で太陽とともに目覚めて太陽が沈むと仕事を終えるスタイルの農業に従事する70代の友達に囲まれているうちに、気づけば自然と生活のリズムが整い、肩の力が抜けていました。仕事でもプライベートでも、「自分が心地良いかどうか」が判断基準に変わったことで、心にゆとりを持てるようになったのです。
自分自身を押し殺すのではなく、日々の暮らしの中で感じる感覚や違和感に耳を傾けながら、それを大切にすることが、真のウェルビーイングにつながるのではないでしょうか?ぜひ皆さんも、自分にとっての「心地よさ」を見つけながら、自分らしい選択を一つずつ積み重ねてみてください。