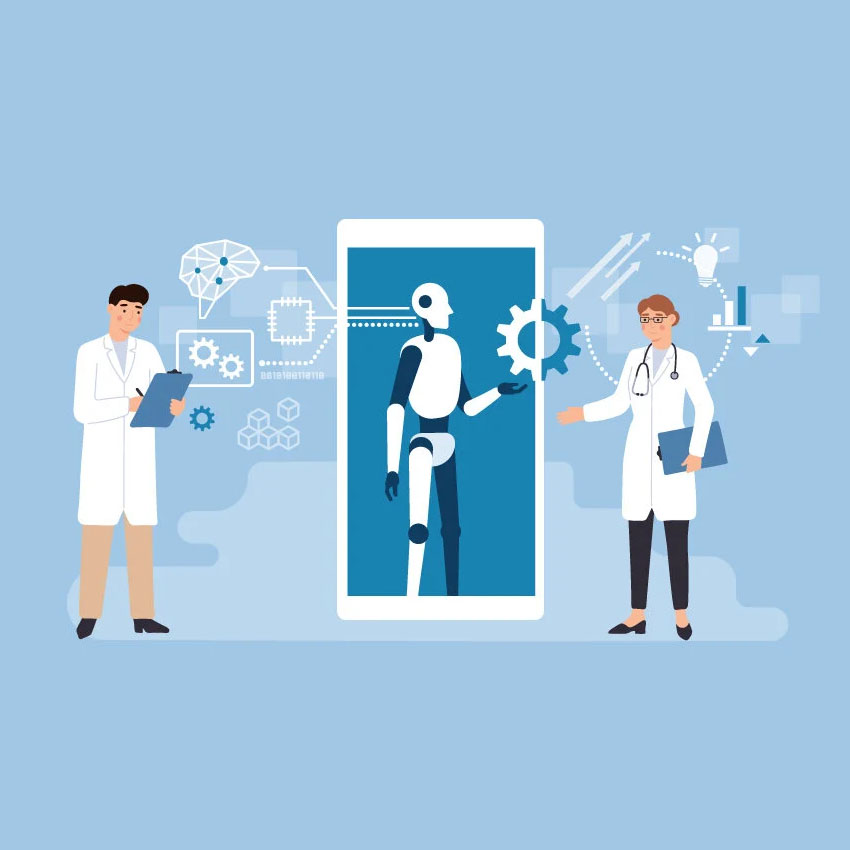医療現場で活躍する動物たち――動物介在療法による心の交流が患者さんにもたらすものとは?
2024.03.25

患者さんが心身ともにより良い状態で病気に向き合うための補助療法のひとつに、動物介在療法があります。アニマルセラピーとして犬と触れあうイベントなどを実施する高齢者施設や小児科病院も見られるようになりました。しかし、治療としての成果が求められる医療機関で、こうした活動を恒常化していくことは決して簡単なことではありません。
そうした中、聖マリアンナ医科大学病院では、緩和ケアチームの一員として「勤務犬」が患者さんに寄り添い、治療意欲の向上に貢献しています。
今回は、小児科医として動物介在療法を第一線で研究されている聖マリアンナ医大の長江先生をはじめ、勤務犬のハンドリングを行うハンドラーであり、看護師でもある兒島さんと溝部さん、リハビリテーション科センター長の佐々木先生より、患者さんの心を置き去りにしないケアの充実を図る取り組みとその意義について教えていただきました。

長江 千愛 先生
聖マリアンナ医科大学病院
小児血液疾患(血友病、各種出血性および血栓性疾患)専門。聖マリアンナ医科大学小児科の講師を務める。同大学病院において、動物介在療法の導入に主体となって取り組むなど、動物介在療法を第一線で研究している。
動物がもたらすあたたかさを実感して

「動物介在療法」とはどのようなものか教えてください。似た言葉に「動物介在活動」がありますが、どのような点が異なるのでしょうか?
動物介在療法(AAT:animal assisted therapy)は、動物の力を借りて患者さんの情緒的安定や闘病意欲の向上を図るために実施する補助療法の一つです。単なる動物と患者さんの交流にとどまらず、個人の症状や背景に沿った治療計画を立案・実施することがポイントとなり、実施後はどのような効果があったのか、どのような課題が残ったのかを、ハンドラーをはじめ主治医や担当看護師ととともに振り返り、次の介入方法につなげていきます。当院が導入しているのも、この動物介在療法です。「勤務犬」という呼び方は、医療チームの一員という想いを込めて当院が独自につくった言葉で、ファリシティードッグや介助犬との差別化を図っています。
一方で、動物介在活動(AAA:animal assisted activity)は動物との触れ合いを目的としており、介護・福祉施設などでも取り入れられています。日本で行われている「アニマルセラピー」の多くはこのAAAに分類されます。
聖マリアンナ医大は国内で唯一動物介在療法を行っている大学病院ですが、そのきっかけは何だったのでしょうか?
当院のAATは、2012年、白血病で入院していた1人の少女による「ワンちゃんに会いたい」という願いから始まりました。彼女は自ら、ファシリティードッグとして活躍していたベイリーとその活動団体に手紙を送り、縁あって当院に来ていただくことができました。その際、「病院にワンちゃんがいる!」という噂を聞きつけた患者さんがたくさん集まってこられました。小児科の子どもたちはもちろん、そのご家族やさまざまな世代の患者さんがいらっしゃいました。臨床の現場において、患者さんが病状の進行や今後の生活に不安を感じ、笑顔がなくってしまうことは少なくありませんが、ファシリティードッグが当院に来た時の、患者さんたちの生き生きとした笑顔を見て、動物が持つ力、AATの大切さをありありと実感しました。こうした想いのもと集まった、私を含む医療従事者5名で、AATを当院に導入するために動きはじめました。
3年半を要したAAT導入までの道のり

動物介在療法の導入に向けて、どのように取り組まれていったのでしょうか?
導入にあたり最も重要となったのは、いかに周囲の理解を得て、味方を増やしていくかでした。検討当初、関係者の多くは総論賛成・各論反対でした。動物が医療チームの一員として病院で活躍することに対しては好意的であるものの、突き詰めていくとアレルギーのある患者さんはどうするのか?衛生面は?資金は?――と、具体的な懸念点はいくつも挙がりました。そうした課題を一つひとつクリアしていくため、奮闘の日々が続きました。理解を得るための啓蒙活動として、どうして病院に犬がいる必要があるのか、その意義を伝える講演会を繰り返しました。病院の講演会では、異例ともいえる130名以上の方に一度の講演でご参加いただくなど、それだけ興味を持ってくださっていることを実感しましたし、勤務犬導入希望の署名活動では2日間で2,000名以上の署名が集まりました。
日本介助犬協会と日本盲導犬協会にご協力いただけたことも大きかったです。両協会のPR犬によるAAAを50回以上行い、患者さんをはじめ医療スタッフが犬との触れ合いによる効果を実感する機会を設けました。日本介助犬協会より勤務犬となる犬をお貸しいただくことに加え、ストレス状態や健康管理も定期的にチェックしていただけることになりました。さらに、勤務犬のパートナーとなるハンドラーの指導教育についても力をお貸しいただきました。ハンドラーを雇うには高額な資金が必要となる中で、私たちは当院の医師や看護師が兼務するという選択を取りました。各部署とのコミュニケーションが取りやすいですし、何より当院のことをよく理解してくれているからです。ただ、看護のプロフェッショナルであっても、犬のトレーニングに関しては初心者です。日本介助犬協会指導のもと、犬に関する知識や扱い方を、合宿などを通してしっかり学んでもらいました。
さらに、衛生面では当院の感染制御部に協力していただいたことで感染制御の態勢を整えることができ、資金面では本学の同窓会に援助を頂きました。犬のプロと感染のプロ、そして金銭面の援助――各過程でキーパーソンの協力を得られたおかげで、2015年4月、ついに夢が叶い、AATを正式に導入することができました。

「治療」として、いかに意味のある介入ができるか

勤務犬は、どのような活動をされているのでしょうか?
現在当院では、3代目の勤務犬となるゴールデンレトリバーのハクが活躍しています。活動内容は緩和ケアへの介入や臨床サポート、手術室までの付き添いやリハビリの介助・付き添いなど多岐にわたります。勤務は週に2日で、1回のAATは約30分程度、患者さんと勤務犬の1対1の取り組みとなります。初代勤務犬であるミカ、そして、2代目のモリスからハクにバトンが受け継がれるまでの8年間で、計421件ものAATが実施されました。
大切なのは、勤務犬が介入する目的や方法、介入後の目標を患者さんの症状や状態に応じて明確に定めることです。AAT の後は必ず振り返りを行っており、アンケートでは97%の看護師が本来の目的に沿った活動ができたと回答しています。患者さんご本人やご家族へのアンケートでも、「とても良かった」、「良かった」との回答が98%を占めました。また、AATの前後でフェイススケール※を評価すると、表情の変化に有意的な結果が出ることもわかっています。AATにおける科学的エビデンスを示すために、AATの前後で患者さんの唾液中のストレスマーカーであるコルチゾールやアミラーゼ、オキシトシンの分泌量を測定する研究を進めています。
※ 痛みの表現を言語や数値ではなく、人の顔の表情によって評価するスケールのこと
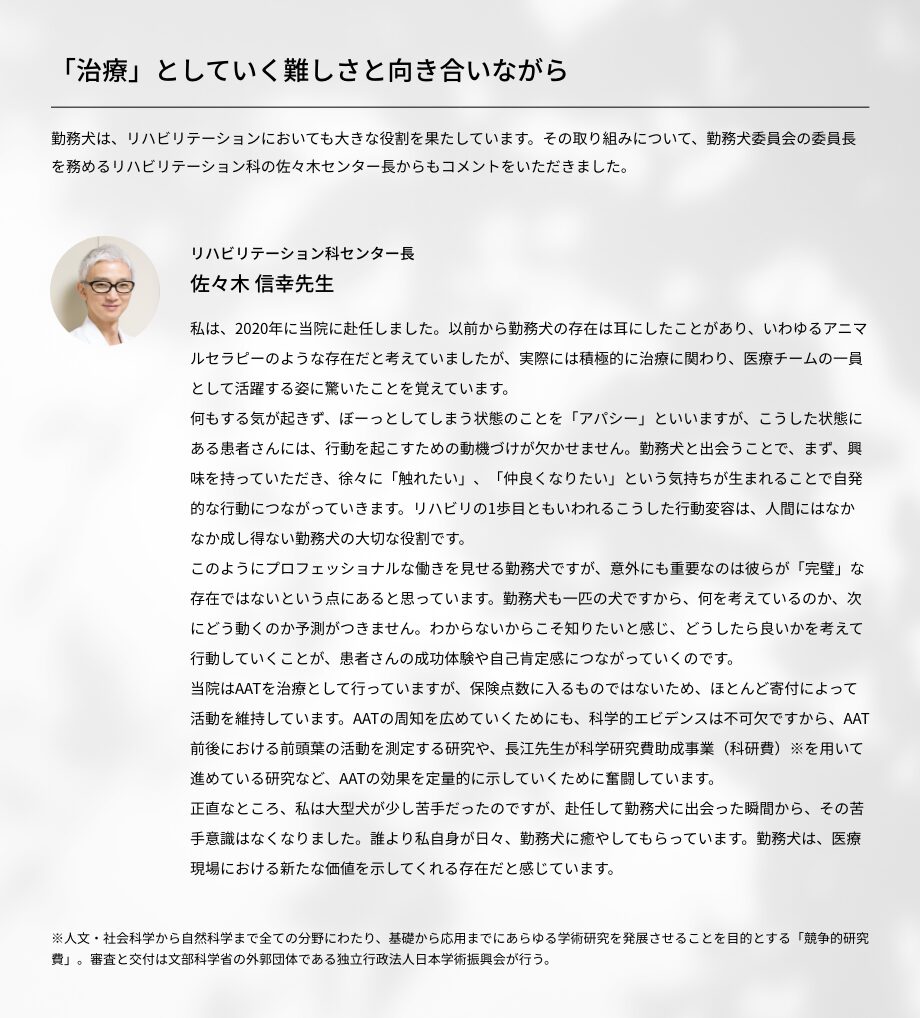
動物がつくってくれた“きっかけ”を、“愛ある治療”へつなげていく

勤務犬は患者さんやご家族にとって、どのような効果をもたらしていると実感されていますか?
「やっぱり動物の力は、すごいです。薬では治療できない最もデリケートな部分を勤務犬が、ケアしてくれました。それは、息子の入院生活の中で最も大切なことだったと思います。」――白血病で闘病していた15歳の男の子のお母さんからいただいた手紙の一部です。彼は闘病生活の中で閉ざしてしまった心を、勤務犬と触れ合う中で、次第に開いてくれるようになりました。もう1人の15歳の白血病の男の子は周囲の人を思いやるとても優しい性格でした。親や医療関係者に心配をかけないようにと、入院後もずっと弱音を吐かず「大丈夫、大丈夫」と強がっていたのです。私たちはは心配しながらも、どうすることもできないでいました。そうやって自分を精一杯保とうとしていたのだと思います。しかし、ある日、勤務犬の前で「どうして、僕が…。僕がみんなに心配と迷惑をかけている。僕さえいなければ…。」と弱音を吐いてくれたのです。悲しみを抱え込んだ状態を誰にも見せられず一人で耐えていたのは辛かったはずです。勤務犬のあたたかさが強がる心を溶かしてくれた瞬間でした。
16歳の自閉症の女の子は、顎下腺の腫瘍を除去する手術を長年ためらっていました。手術も怖いし、声を失うリスクがあったからです。腫瘍があるため、どうしてもさまざまな画像検査が必要になりますが、その際は、大人5人がかりで患者さんの体を押さえつけながら画像を撮影していました。検査の必要性も理解してもらえず、無理やり検査をしている状況に、医療従事者として本当にこれで良いのだろうかという思いが常にありました。しかし、勤務犬と仲良くなり、勇気と覚悟と、将来への期待を持てるようになり、自分の意思で手術を受ける決断をし、手術当日も勤務犬のリードを持ちながら自らの足で笑顔で手術室に向かうことができたのです。お母様からは、「個性を尊重しながら、本人の意思で手術に踏み切れたことに、障がい者医療の新しい姿を見ました」と感謝の言葉をいただきました。4歳の先天性声門下狭窄症の男児は月に1回繰り返される手術に恐怖を感じ、手術室に入るのを全身で拒み、泣いて暴れる毎日でした。それが、入室前に勤務犬との時間を提供しリラックスさせ、サブリードで信頼関係を保ちながら手術室までの歩きを楽しく演出することにより、笑顔で手術室に自分の足で入ることができ、入室時間が40分から5分に短縮したのです。「諦めないでよかった、勤務犬に会えてよかった」と涙を流すご両親の姿が今でも忘れられません。
AATの症例は小児科だけではありません。ターミナルケアでは、余命1カ月の患者さんの恐怖感に寄り添う中で、患者さんの言葉や表情が徐々に前向きなものへと変わっていきました。亡くなる最後まで、勤務犬と触れ合うAATの時間を楽しまれました。
また、意外なところで有効性が認められたのが切迫流産の患者さんです。多くの患者さんは、絶対安静が必要な不安な状況により孤独になりがちなのですが、勤務犬が来るとカーテンを開けて外に興味を持ってくださるようになるのです。患者さん同士がつらさを共有し合えるようなコミュニケーションのきっかけにもなっています。
最後に、動物介在療法が持つ意義と展望をどのようにお考えでしょうか?
誤解を与えない言葉を選ぶのは難しいですが、8年間取り組んできて感じるのは、やはり動物は人間にはない力を持っているということです。しかし、それはあくまでもきっかけに過ぎず、そこからより良い治療につなげていくのは人だと感じています。看護師や主治医をはじめとした医療スタッフ、また、ご家族がいかに患者さんを思いやるかで、患者さんの心にもたらされるものは変わってきます。その上で、間違いなく勤務犬はその一助になってくれますし、言葉では表現できない特別なぬくもりや安心感を与えてくれます。そして、つらい状況の中でも、患者さんが本来持っている人格や人を思いやる優しさ、自分が必要だと感じられる自己肯定感を取り戻させてくれ、病気や事故によるけがと向き合う気力をも引き出せる存在だと感じています。
家に帰ることができない入院患者さんにとって、院内で動物と触れ合える時間はどれほど貴重で、癒やされ、安らげるひとときでしょうか。私たちは今後も、当院の掲げる“愛ある治療”のために動物介在療法を継続していきます。動物介在療法の認知がさらに広がり、その意義をぜひ知っていただけたら嬉しく思います。