陣崎雅弘先生に教わる、 医療とAIの幸せな手のつなぎ方
2023.07.12
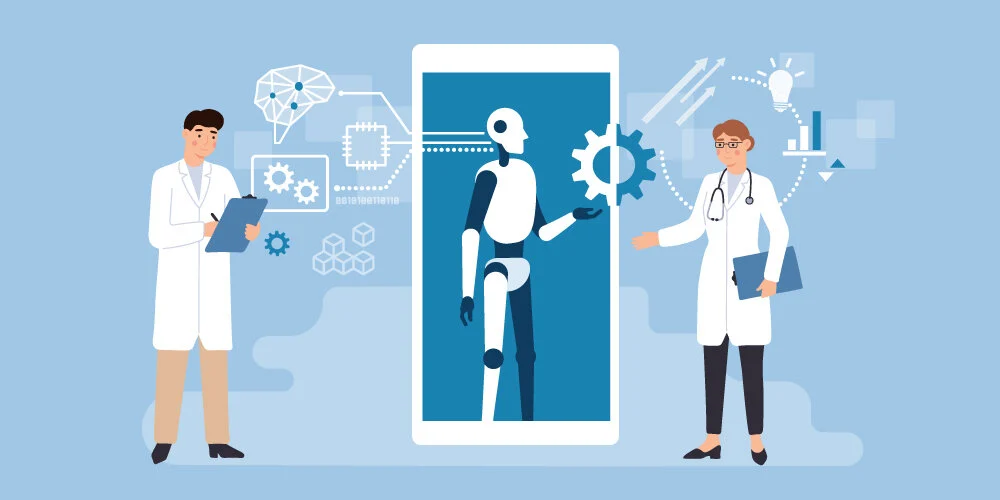
昨今の医療界では、AI(人工知能)の活用が進んでいます。医療現場でどのように用いられ、受診する私たちにはどのようなメリットがもたらされるのでしょうか。
今回は、医療AIの第一人者である陣崎先生より、その潮流や取り組み、そしてAI活用を進める上で持つべき意識について教えていただきました。

陣崎 雅弘 教授
慶應義塾大学医学部 放射線科学教室 教授
1987年、慶應義塾大学医学部を卒業し放射線診断科に入局。日本鋼管病院、ハーバード大学付属 Brigham and Women’s Hospital 留学後、慶應義塾大学放射線診断科講師、同准教授を経て、 2014年より現職。
AIを医療に導入する上での課題

医療界におけるAI技術の活用と、その変遷について簡単に教えていただけますでしょうか。
人の知能に匹敵しうる高精度なAIの実現は、研究者にとって長年の夢でした。画像診断はAIの対象として早くから取り組まれ、2000年代にはアメリカで機械学習を用いたマンモグラフィーの自動診断ソフトがFDA※1 に認可もされました。しかし、結局ほとんど使われることなく終わりました。
このような中、2015年頃から普及し始めたディープラーニング(深層学習)によって、AIの画像診断への応用が広がっていくのではないかという期待が大きくなりました。実際にこの数年間の中で、日本でもいくつかのAIはPMDA※2 の承認を得られるようになってきました。しかし、日本ではこれまでは医療現場でそれほど用いられておりませんでした。その理由の1つは、高度な業務は人がやってもよいと思っているものが多く、それを代替するには相当な精度が要求されることです。一方、やりたくないと思っている業務であれば、そこそこの精度でも導入されるように思います。もう1つは、AIがブラックボックスであり、判断の根拠が不明なので、どこまで信用してよいのかわからないという要素も大きいです。3つめは保険収載がほとんどされていないために、導入すると病院は出費が増え、ハードルがあることになります。
AIツールが「開発される」ことと、それが現場で「実装される」ことは別問題だったのです。
では、現時点ではどのようにAIを取り入れることが有効とされているのでしょうか。
もともとITは高スキルを持った人に有効であったと思います。そこでAIが登場してきたときに、多くの人はAIも画像診断のような高スキルの業務に有効と考えたのだと思います。しかし、実際には上記のように医療の高スキルの業務を対象とするにはハードルが高いことが多く、むしろ低スキルの業務への導入の方が有用であるように思います。例えば薬剤搬送ロボットや人搬送ロボット、薬をミスなく調剤するロボットなどが代表的で、AIを活用して業務を効率化することは歓迎されるように思います。
また、病院の受付や問診、同意取得などをデジタル化することで、医療従事者の負担軽減のみならず患者さんもスムースな受診が可能になるという恩恵を受けます。医療従事者側の業務が効率化された分、診療や専門的な研究に時間を確保できるため、医療の質向上、将来的には高度な医療の提供にもつながっていくといえます。
※1 FDA(Food and Drug Administration):アメリカ食品医薬品局。保健福祉省に属するアメリカの政府機関で、食品添加物の検査や取り締まり、医薬品の認可などを行う
※2 PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構):医薬品、医療機器や再生医療等製品に関する承認審査、安全対策、健康被害救済の役割を担う公的機関
キーワードは「モノタスク」

なるほど。より高度な診療の助けになるようなAI活用は難しいのでしょうか?
AIの問題点のひとつは、AIは基本的には1つの課題を学習しているので、その課題にしか対応できない“モノタスク”であることです。しかし、例えばCTやMRのような放射線画像診断業務の場合、1症例の画像データに肺、心臓、肝臓、すい臓、腎臓、脾臓など多くの臓器が映っていて、それぞれの臓器に考えられる疾患が多数あります。人による読影は、これらの非常に多くの疾患の可能性を瞬時に拾い上げたり見分けたりする“マルチタスク”業務です。モノタスクのAIをこのような業務に用いるとなると、症状などから想定されうる疾患を挙げて、それらを指摘できる多数のAIを読影業務時に稼働させることになるのでしょうが、事前に想定していなかった、いわゆる偶発所見が原因であった場合は、どれだけ多数のAIを投入していても正しい診断に到達できないことになります。
その結果、もう一度、偶発所見を見逃していないかを人が再確認する必要があるので、AIを活用すると読影業務のコストが高くなるような気がします。その意味では、読影業務のAIはあってもよいけれど、なくてもそれほど困らないもののようで、実際、画像読影のAIは世界中を見てもほとんど使われていません。無論、読影医の見逃し防止などの負担軽減のために、コストはかかりますが読影補助としてAIを活用するというのはとても良い方向だと思います。
このようなことを考慮すると、AIが有効なのは、例えば診断名がすでに確定できていて、その重症度や悪性度を画像から推定するとか、脳動脈瘤健診においてはMR画像からの脳動脈瘤の検出のみを判断すればよいのでその業務を任せる、といった1つの課題に落とし込むことができるものです。すなわち、高度な診療課題がAIに適しているかどうかは、その作業が「マルチタスク」なのかそれとも「モノタスク」なのかを考えてみるとよいです。「マルチタスク」に活用しようとすると、思ったほど成果を上げにくいかもしれませんが、その場合は「マルチタスク」業務の中で課題を限定して補助的に用いてみると有効な場合はあります。また、「モノタスク」であるところにAIを活用することも有効であると思います。
陣崎先生が期待されているAI技術について教えてください。
おそらく多くの人がそうであろうと思いますが、やはりChatGPTの登場を目の当たりにしますと、これからは私たちが日常的に書いたり話したりしている言語をコンピュータに処理させる“自然言語処理”に大きな期待を寄せることができるように思います。有効な自然言語処理AIがあると、問診、同意取得、カルテ記載などの基本的な診療行為の大部分は言葉や文字で行われるので、医療も大きく恩恵を受けることになります。もっというと、これまで述べてきた“画像認識“を活用するのは一部の人ですが、言葉を用いない人はいないので、“自然言語処理“は全ての人が恩恵を受けることになります。
医療AIの本丸は、画像認識から自然言語処理に転換しつつあると考えています。この領域に関しては私も引き続き注視しながら、さらに研究を深めていきたいと思っています。
「健康長寿」の時代に、AIができること
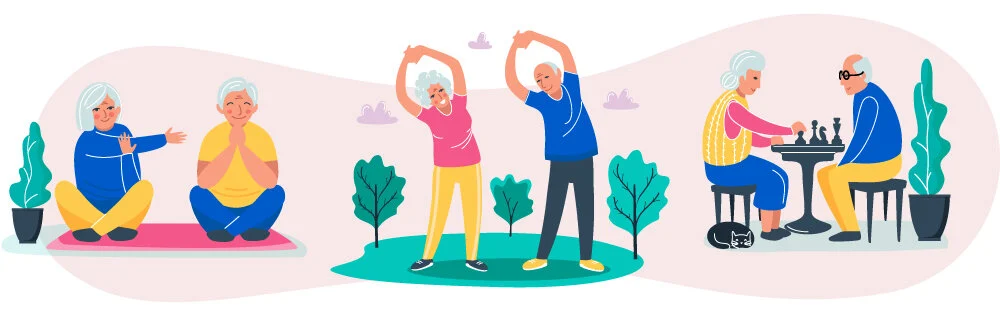
「陽だまり」では、患者中心の医療への転換を図るとともに、病気を予防し、ひいては一人ひとりの心身を満たすウェルビーイングの三つがそろったウェルネスな仕組みづくりが重要と考えています。陣崎先生が研究の先に見据えている「ウェルビーイング」について教えてください。
日本は今や超高齢社会を迎えています。そうした時代に着目していくべきは、「平均寿命」と「健康寿命」の差をなくしていくことです。これまでは、「寿命」を延ばすための医療でした。ある機能が低下したとしても、命に関わらない疾患は優先されてこなかったのです。
しかし、これから必要になるのは、健康で文化的な生活を長く続けるための医療、つまり機能の低下を早期に診断し、機能の維持・改善のための治療を行う、そんな新しい診断学を創っていくことだと思うのです。
その一環として私が行っている研究の一つが、立った姿勢で撮影できるCTです。CT画像は通常、寝た状態で撮影しますが、嚥下、排尿、歩行などの機能は寝ていると評価できません。また腰痛のように、寝ているときは何でもないのに立つと症状がでる病態も数多くあります。従来の寝ている状態での検査では日常で感じている不調や機能異常を捉えきれません。
不調を感じる状態に近い体位での画像撮影を行うことで、その原因やケアすべき部位を明らかにすることができ、機能の維持・改善のための治療が可能となります。その結果、超高齢化社会における自律的な生活を維持し、ひいては健康寿命を伸ばすことにもつながるのです。
もう1つ研究テーマとして捉えているのは、病気になった人だけではなく、未病「=病気と診断されていないものの、健康な状態から離れつつある状態」の人と、後病「=治療終のケアを必要とする状態」の人も総合的に一気通貫に診ていくという、いわゆる『ペイシェントジャーニー』という視点でのサービス提供です。病気になるかもしれない不安、病気を克服した後に社会に復帰できるのかという不安、この両方の不要な不安を解消していくことが、ウェルビーイングな社会の実現に重要だと考えています。病気を経験した人は、すでに診断がついている状態のため、すべき治療や想定範囲が特定されています。つまり、「モノタスク」に近い解析となるため、後病におけるケアにおいてはAIを活用しやすいといえます。
病気や健康に対する不安を拭い、自信を持って社会活動をしていただけるような医療を提供できればと考えています。



