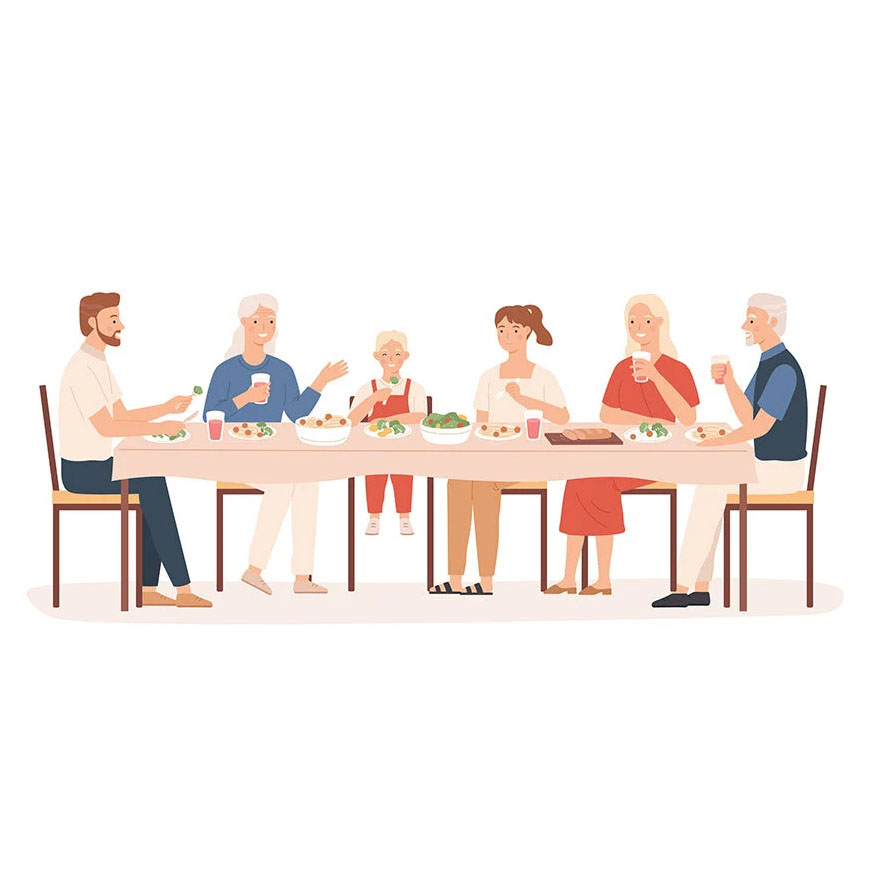アスリートを支える「スポーツ栄養学」、管理栄養士が語る食事戦略[前編]
2025.01.28

パリ2024大会では、アスリートたちの活躍が世界中に感動を届けました。その活躍を支える上で欠かせない要素の一つに「食」があります。パフォーマンスを左右する「食」を科学的にサポートするために発展してきたのが、「スポーツ栄養学」という分野です。
今回は、アスリートへのスポーツ栄養サポートを行っているエームサービスの管理栄養士、松岡未希子氏にお話を伺い、スポーツ栄養学における同社の取り組みや、ビジネスパーソンにも応用できるパフォーマンスを向上させる食習慣のヒントを教えていただきました。

松岡 未希子 氏
エームサービス株式会社
管理栄養士/公認スポーツ栄養士/健康運動指導士
高校生の頃、趣味のサッカー観戦をきっかけに、アスリートを支える栄養士の存在を知り、アスリートを栄養面からサポートしたいという思いから栄養士を志す。2015年に公認スポーツ栄養士資格を取得し、 現在はエームサービスでさまざまな形で栄養サポートに携わる。また、同社における栄養士・管理栄養士の教育体系の構築や事業所運営のサポートにも取り組んでいる。
身体活動量の多い人に特化した栄養学

スポーツ栄養学とは、どのような学問なのでしょうか?
わかりやすく説明すると、身体活動量が多い人の体で起こる変化に応じて、「何を、いつ、どれだけ、どのように摂取するか」を体系化した学問です。例えば、運動やスポーツで身体活動量が増えると、エネルギー消費量や発汗量が増加、筋損傷などが起こります。これらの変化を生化学的に分析し、それに基づいた栄養学理論や実践スキルを体系化したのがスポーツ栄養学です。
日本では、1980年頃にスポーツ選手向けの食事本が出版されたのを機に「スポーツ栄養」という言葉が広まりました。その後、1990年代にかけて研究が進み、科学的なエビデンスが蓄積される中で、理論に基づいたアスリートのサポートが可能になってきました。歴史はまだ30〜40年と浅いですが、現場での活用によって進化しています。
スポーツ栄養学は、どのような場面で活用されているのでしょうか?
スポーツ栄養学と聞くと、一流アスリートのみに活用されるものと思われるかもしれませんが、日常的にスポーツに取り組んでいる方々も対象に含まれ、年代や競技レベルを問わず身体活動量が多い方に活用できます。
どのような方が対象でも、体の大きさや活動量に応じて「何をどれだけ食べるか」という基本の考え方は変わりませんが、対象者に応じてアプローチを変えています。例えば、成長期にあたる小中学生を対象とした場合は、体づくりを優先し、その根幹となる食事の基礎知識を伝える「食育」に重きをおいたサポートが求められます。一方、プロのアスリートでは、すでに食事や体に関する基本的な知識を持つ選手が多いため、体づくりの目的やオフシーズンや試合時期に沿った食事アドバイスなど応用的な内容が中心となります。
選手がなりたい自分へ、栄養で導く

エームサービスでは、スポーツ栄養分野においてどのような事業を展開しているのでしょうか?
当社が提供するスポーツ栄養サポートは、大きく分けて「食事提供」と「栄養教育」の二つです。学生寮や社会人実業団などのスポーツ寮、養成所など全国約60か所の施設で実施しています。
「食事提供」では、チームスタッフの皆様とも連携し、競技特性やトレーニング内容などに応じた食事を各施設の食堂などで提供しています。また、「栄養教育」では、食事の大切さや、自分の体に合った食事と栄養の選び方についてお伝えするセミナー形式のものや、選手一人ひとりの運動強度、体組成、環境などをアセスメントし、必要な栄養素と量を明確にした上で、パーソナライズされた食事についてアドバイスする個別サポートを行っています。例えば、男性の野球選手と女性のフィギアスケート選手では、競技特性だけでなく、求められる体づくりも大きく異なります。それぞれの選手に合わせた栄養サポートは、まさにスポーツ栄養士の腕の見せ所です。私たちの最終的な目標は、選手自身が「何をどれだけ食べれば良いのか」を理解し、自ら選択できるようになることです。栄養士がそばにいなくても、自分で食事を管理できる力が自然と身につくような支援を目指しています。
最適なサポートをするために欠かせない対象者へのアセスメントは、どのように行われるのでしょうか?
まず、選手の食事摂取状況を把握します。「いつ・何を食べているのか」だけでなく、毎日の練習量や試合のスケジュール、学業など、競技以外の生活リズムも確認します。その上で、選手と目標を共有して目指す体づくりに向けて具体的な目標値を設定し、過不足している栄養素や直近の体組成変化を分析し、食事の改善案を提案します。
例えば、カルシウムが不足している場合、一般的には牛乳を食事に取り入れることを提案しますが、乳製品が苦手な選手にはカルシウムを多く含む野菜類を提案するなど、本人が無理なく続けられる方法を見つけます。これらの提案は期間を設定して実行し、進捗を確認した後に、次の目標を設定する、いわゆるPDCAサイクルを回しながら、選手が理想の自分に近づけるようサポートしています。
選手の食事の内容を把握するには、生活の細かいプライベートの領域にも踏み込む必要があり、信頼関係の構築は効果的なサポートの根幹となります。例えば、控えているお菓子類を食べたくなることは誰でもありますが、アスリートも例外ではありません。そのような場合も、「栄養士は怒る存在」と思われてしまうと、食事の実態が把握できなくなるため、頭ごなしにアドバイスするのではなく、選手にとって「目標達成の近道を教えてくれる頼れる存在」になることが重要です。このように効果的なサポートを提供するには、選手の食事内容の把握だけでなく、性格や生活スタイル、競技への想いを深く理解することが欠かせません。
アスリートにとって食事は体づくりに不可欠である一方、日々の楽しみの一つにもなり得ると思います。その点はどのようにバランスを取っているのでしょう?
そうですね。基本的に食べるタイミングと量を守っていれば、「食べてはいけないもの」はありません。選手の「食べたい」という気持ちに寄り添いながら、パフォーマンスに影響が出ないようバランスを取ることを心掛けています。例えば、唐揚げが好物の選手に対しては、脂質を多く含むため、試合前は控え、「試合後のご褒美にしましょう」と提案し、食べる楽しみと試合に向けたコンディションの調整を両立させます。また、炭酸飲料を毎日飲みたい選手には、無糖のものを勧めたり、飲む頻度を調整するといった提案をしたりしています。
日々プレッシャーの中で闘っている選手にとって、食事の時間がほっとできるひとときになるような工夫もしています。当社の事業所では、誕生日の選手にはお祝いメニューを用意するなど、食事がモチベーションの一助となるような演出も大切にしています。
後編では、スポーツ栄養学に基づいたビジネスパーソンへのヒントや、スポーツ栄養領域の展望について教えていただきました。後編はこちらをご覧ください。